朝鮮人日本軍特別志願兵ーまとめ6
ライター:鄭安基(博士、経済学者、東アジア歴史研究家、反日種族主義の共同著者)
翻訳:崔榮黙(メディアトラジ管理者)
6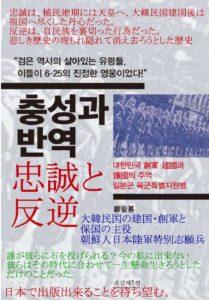
六つ目は、植民地軍事動員の経験と遺産は何か。 先に検討したように、陸軍特別志願兵は解放後の大韓民国の建国とともに、自由と繁栄を担保する物理力の核心であった。 アジア太平洋戦争期、日本の植民地軍事動員が1945年以後、東アジア帝国の独立国家創成に及ぼした衝撃と影響は、単に大韓民国に限られるものでもなかった。 1940年代、東南アジアにおける日本の占領と軍政は、現地の人々のナショナリズムを刺激し、独立への熱望を高めるのに決定的に貢献した。 日本は、政治的独立を保障することを条件に、各地の民族主義者を取り込み、原住民の軍事動員の先頭に立った。 いわば“費用の最小化と効用の極大化“という軍政戦略だった。
一方、東南アジア各地の“協力エリート“たちは、対日協力を通じて、長年の民族的課題であった独立のための物理力確保のてこ(梃子)として活用した。 そこで、アジア太平洋戦争期における日本軍政下の東南アジアは、いわゆる“対日協力の全盛時代“を迎えた。 1943年11月、東南アジアの“協力エリート“は大東亜会議に参加し、日本との軍事同盟を結成し、連合軍に対する宣戦布告した。 しかし、ビルマ·アウンサンの事例のように、日本軍の戦況が1944年末以来、絶望的な抗戦期に変わり、連合軍と連帯して抗日武装闘争に急変した。 1940年代の東南アジア民族主義者の対日協力は、日本に対する思想的共鳴ではなく、独立という民族的課題の達成のための戦術的選択肢に過ぎなかった。 その点で協力と抵抗の境目は極めて曖昧で不明瞭だった。
1940年代、日本軍が東南アジア各地で養成した義勇軍は、インドネシア·ジャワの郷土防衛義勇軍(PETA)3万5500人をはじめ、計約11万9000人に達した。 1943年10月、日本軍が創設したインドネシアPETAの事例のように、“強健な体力と一定の知力を備えた青年たちを動員し、徹底した軍事訓練を実施した。 これらは後にインドネシア国軍の中核“となった。 彼らは独立のための強烈な国防意識を内面化し、国家と民族の守護者を自任した。 インドネシアの初代大統領スカルノ(Soekarno)と第2代大統領スハルト(Soeharto)もPETA出身だった。 1941年12月に創設されたビルマ義勇軍(BIA)は、1943年12月にバーモウ(Ba Maw)のビルマ共和国の建国とともに、ビルマ国民軍(BNA)を再編した。 BNAの初代国防長官は、“ビルマ建国の父“と言われているアウン·サン(Aung San)だった。 1943年に建国したフィリピン第2共和国の第3代大統領ジョセ·ラウンネル(José Paciano Laurel)もフィリピン愛国同志会の創設メンバーだった。
前の第14章で検討したインド国民軍(INA)4万5000人は、1944年インパール(Imphal)作戦が失敗し、英印軍の捕虜になってしまった。 1945年10月、インド政庁はこのうち2万人を“大英帝国の反逆者“と烙印を押して、英印軍の軍法会議に付託した。 だが、“インド国民軍は人道のために戦った愛国者“として即時釈放を求めるインド人社会の大きな支持を受けた。 19446年2月、インド軍の水兵が反乱を起こし、ムンバイ、カラチ、カルカッタで数十隻の艦艇を占拠し、“インド国民軍海軍“を自任した。 インド軍兵士も反乱軍に逮捕と発砲を拒否した。 インド国民軍裁判はインド独立の決め手となった 。これら“大英帝国の反逆者“だったインド国民軍は1947年8月、インド共和国建国とともにインド軍創設の主な人的資源であった。
1945年8月の終戦後、台湾出身の陸軍特別志願兵は朝鮮人と違って過酷な運命に立たされた。 これらは1940年代、日本、中華民国、中華人民共和国によってアジア太平洋戦争、第二次国共内戦、そして1950年の朝鮮戦争に動員され、消耗してしまった。 しかし、1949年~1969年、中華民国の蒋介石総統は旧日本軍将校(約83名)で構成された“白団“という非公式軍事顧問団を編成し、彼らを秘密裏に招聘して国民党軍の精鋭化のための軍事教育に動員した。 いわば、国民党軍は“白団“を通じて弱者戦法の日本軍の遺伝子を修育し、中国共産軍の百万大軍に対抗する“一當百の強軍“に生まれ変わった。
要するに、1940年代の日本の植民地·占領地における軍事動員は意図しない結果であったが、20世紀の東アジア諸国の脱植民地化(decolonization)を促進し、20世紀後半の国民国家創成のための物理力の形成に決定的に貢献した。 “物量主義“ではなく透徹した国家観·死生観·軍人観という“精神主義“を重視する“弱者戦法の力強い国民軍“を創設することができた。
end-

コメントを残す